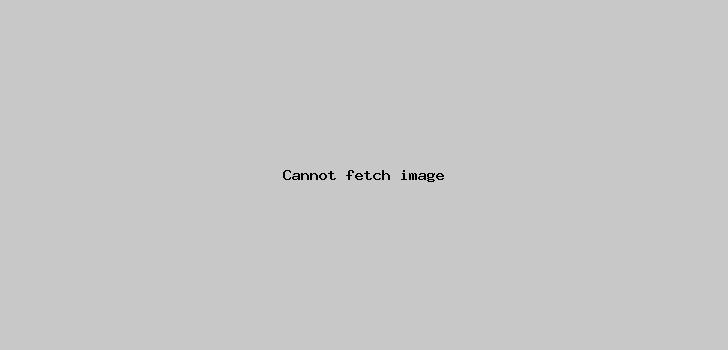
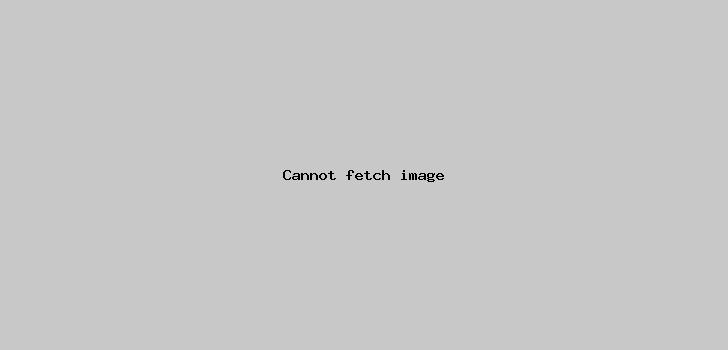
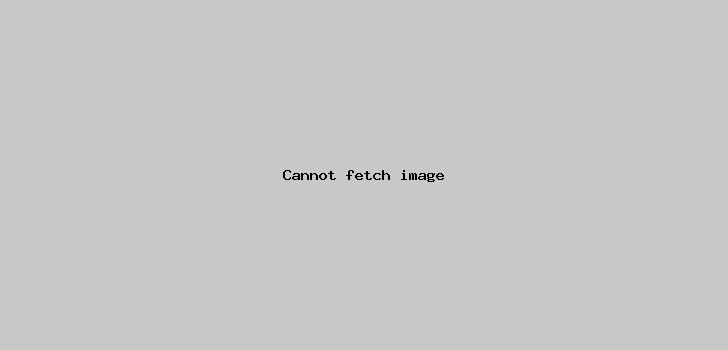
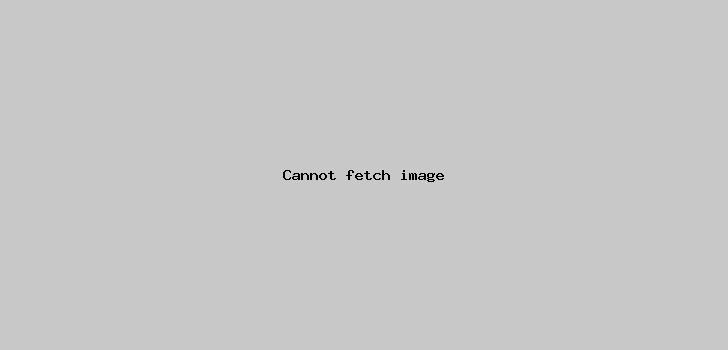
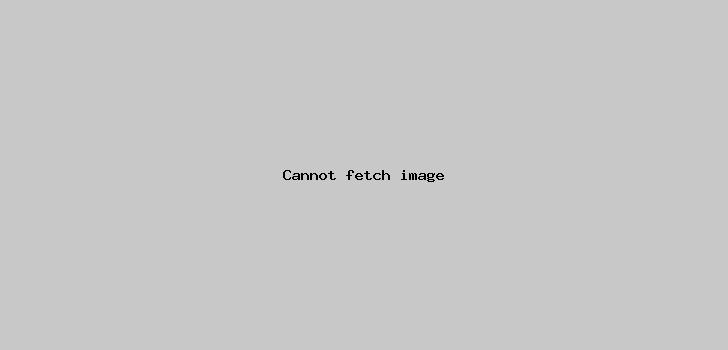
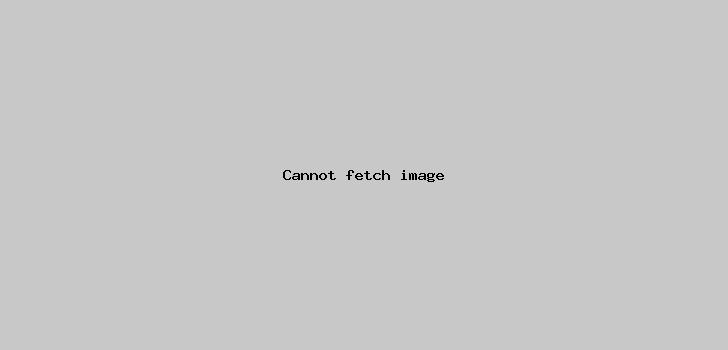
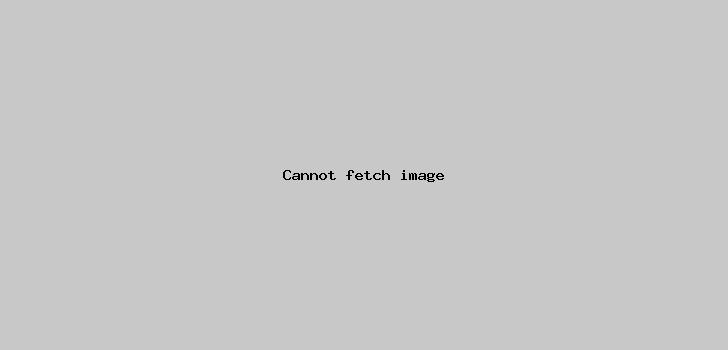
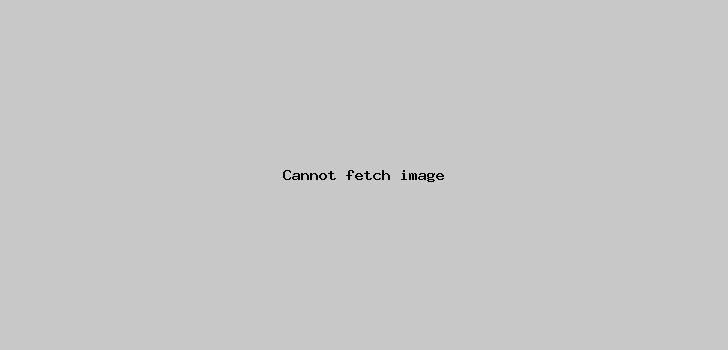
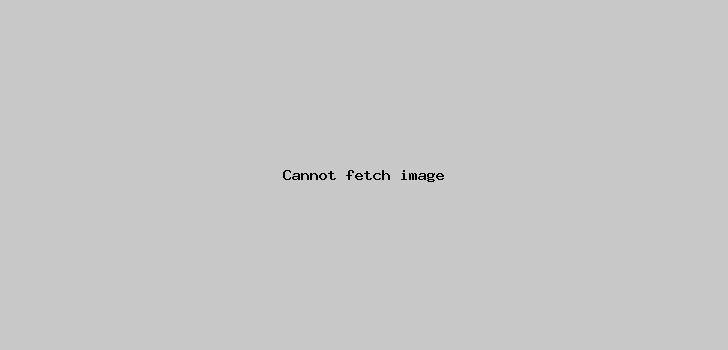
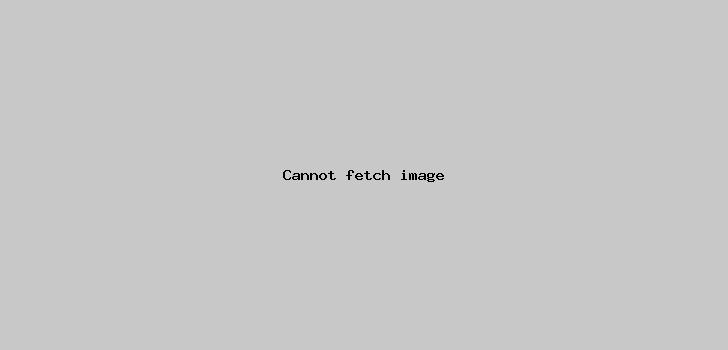
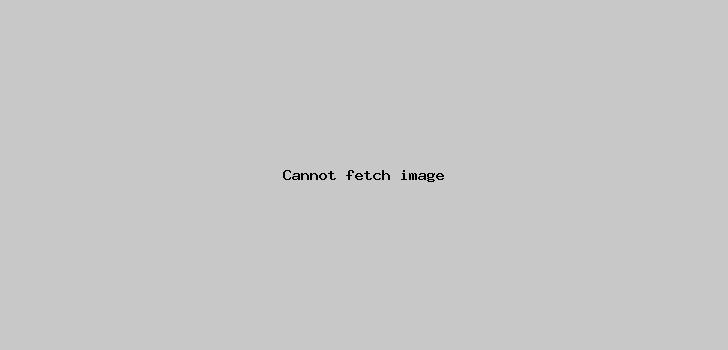
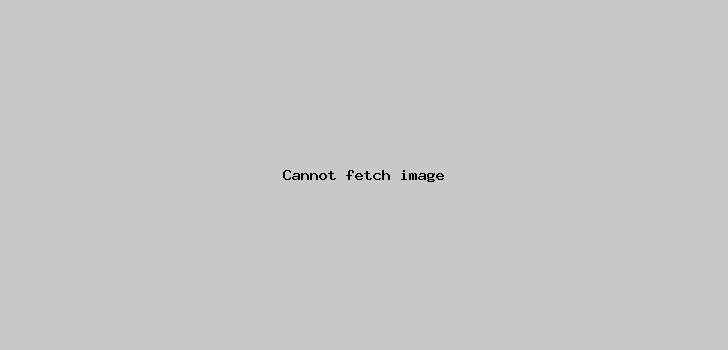
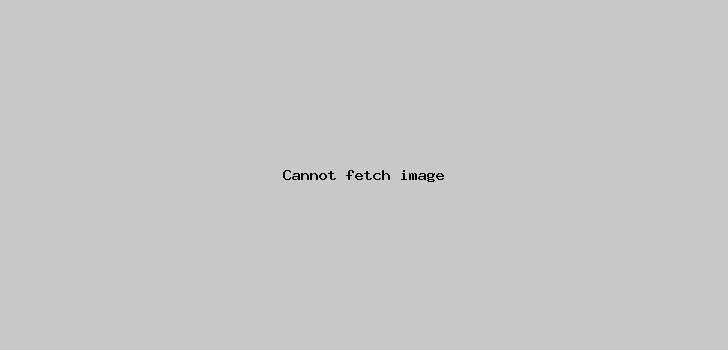
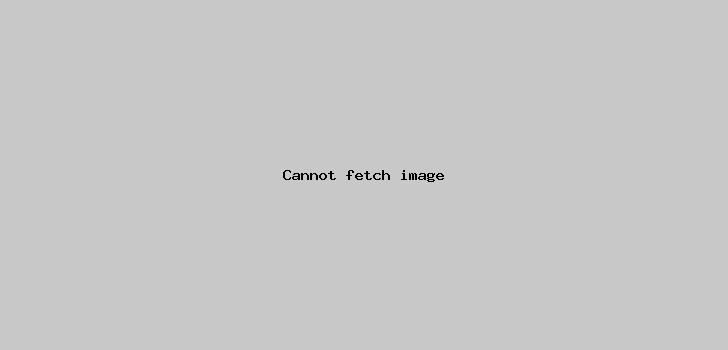
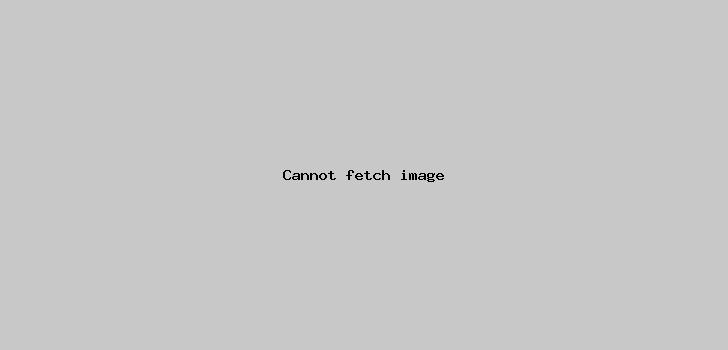
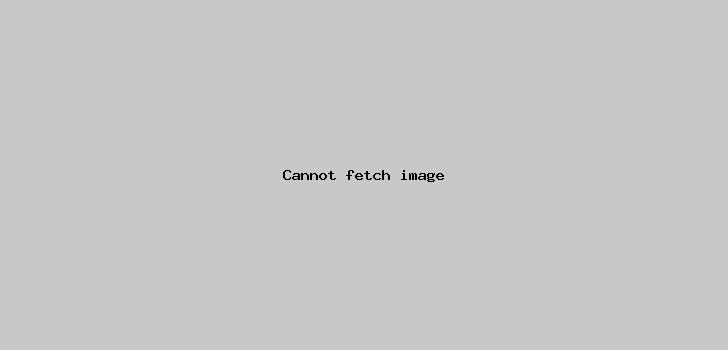
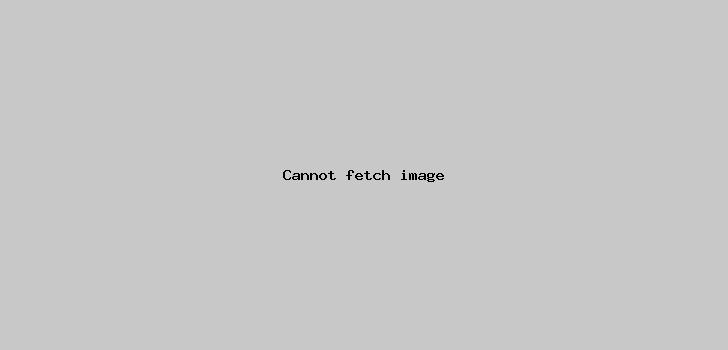
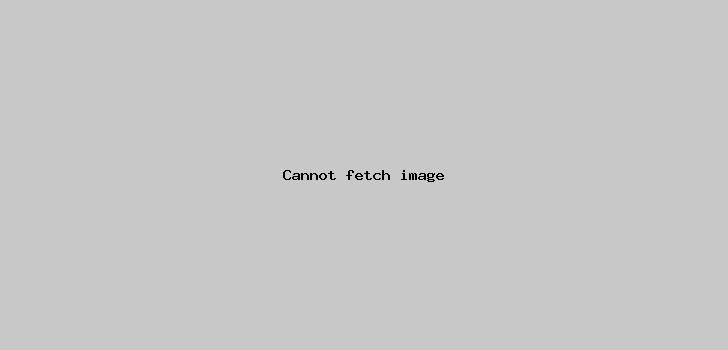
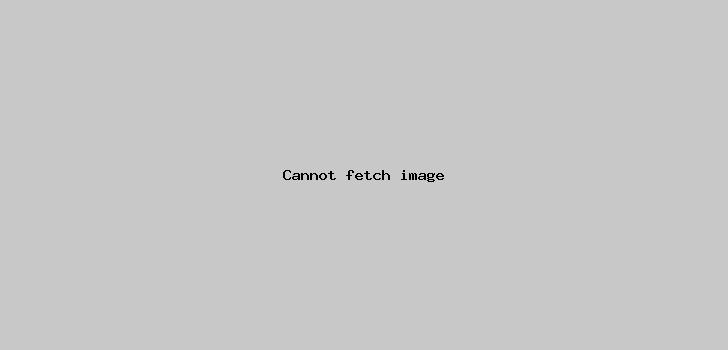
関連記事




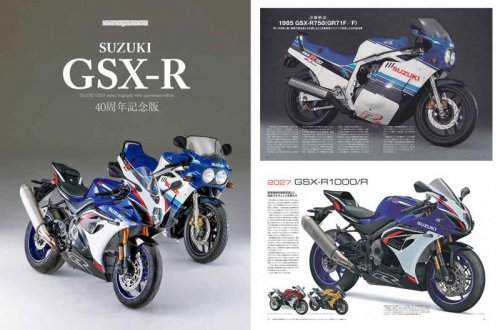



© TopCarNews Network. All Rights Reserved. Designed by TopCarNews