


関連記事

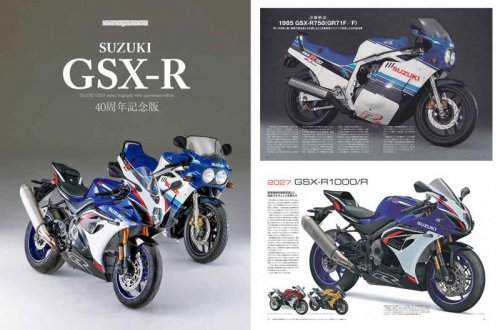







© TopCarNews Network. All Rights Reserved. Designed by TopCarNews